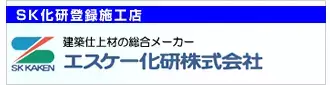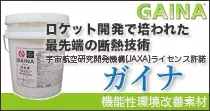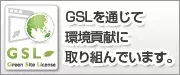編集者プロフィール

はじめまして!
このブログの編集者、岩藤正宏です。私は株式会社イワショウの代表を務め、創業50年の歴史を持つ当社で長年外壁塗装・屋根塗装の業務に携わってきました。建築業界での経験は30年以上、2級建築士、1級建築塗装技能士、外壁診断士、雨漏り診断士など、15の資格を活かして日々の仕事に取り組んでいます。
ブログでは、編集者として、外壁塗装や屋根塗装に関する専門知識を分かりやすく整理し、読者の皆さまに役立つ情報をお届けしています。特に、見積もりのポイントや塗装業界の最新トレンド、住まいを長持ちさせるメンテナンス方法について深掘りした記事を配信しています。
私たちイワショウは、「納得のお値打ち価格」「確かな技術」「丁寧な仕事」をモットーにしています。このブログが、塗装を検討されている方々にとって役立つ情報源となれば幸いです。どうぞよろしくお願いします!
「モニエル瓦を塗装したのに、すぐ剥がれてしまった…」「修理を頼んだら想像以上に高額だった…」こんなトラブルを避けるために、まずは 自宅の瓦が本当にモニエル瓦なのか? を知ることが大切です。
もしあなたがモニエル瓦を 普通のセメント瓦と勘違いして塗装してしまったら? 適切な施工を知らずに補修したら? 数年後、すぐに劣化して 二度手間・無駄な出費 になるかもしれません。
この記事では、 モニエル瓦の正しい見分け方 から 適切なメンテナンス方法(塗装・補修・交換) まで すべて解説 します。DIYでの対応方法、業者に頼むべきケース、さらには 失敗しない業者の選び方 まで網羅。
この記事を読むことで、 あなたの家の瓦がモニエル瓦かどうかを判断できる ようになり、適切なメンテナンス方法を選択できます。 無駄な費用をかけずに、長持ちする施工 を実現しましょう。
さあ、 「モニエル瓦の見分け方」 から 正しいメンテナンス方法 まで、一緒に学んでいきましょう!
モニエル瓦の完全ガイド!見分け方から塗装・補修・交換まで徹底解説
モニエル瓦とは?まずは基礎知識をチェック!
ここでは、モニエル瓦の基本情報をしっかり押さえるために、まずは 「モニエル瓦の特徴」 と 「どこに使われているのか」 を理解しておきましょう。モニエル瓦は、見た目もセメント瓦や陶器瓦と似ているため、ひと目で判断するのが難しい場合があります。しかし、原材料や製造工程、そして表面のコーティングの違いなど、いくつかの特徴を把握することで「モニエル瓦かどうか」をある程度推測できます。正しい知識を持つことは、後々のメンテナンス費用や施工の成功率に大きく影響しますので、ぜひ最初に基礎知識をしっかり押さえておきましょう。
モニエル瓦の特徴とは?
モニエル瓦は、セメントを主原料としつつ、独自の表面仕上げ技術(スラリー層と呼ばれる着色層)を持つ瓦です。通常のセメント瓦とは異なるコーティングが施されており、表面が滑らかで美しい色合いを長持ちさせる特徴を持っています。しかし、その分 塗り替えやメンテナンスには専用の塗料や正しい施工手順が必要 であり、間違った施工をすると剥がれやすいなどのトラブルが起きやすい点に注意が必要です。
なぜモニエル瓦が普通のセメント瓦と違うのかというと、スラリー層 と呼ばれる色付きのモルタル層が表面に施されているからです。このスラリー層によって、色味に深みが出たり、防水性能が高められたりしています。しかし、この層が剥がれやすかったり、経年劣化が進むと部分的に色褪せや雨染みが目立つようになることがあります。さらに、製造メーカーが国内での生産を終えてしまったため、今では生産されていない点 も大きな特徴です。つまり、交換用の瓦が手に入りにくい場合があるので、割れや欠けなどが生じたときに 補修や交換の選択 で悩むケースが多いのです。
- 色ムラや斑点がある:モニエル瓦の表面を見ると、塗料の剥げやすさから部分的に下地が見えていることがあります。
- 艶が独特:セメント瓦よりも若干ツヤ感が強く、特に新品時は鮮やかな色味が特徴的。
- 重量感はセメント瓦に近い:陶器瓦ほど重くはありませんが、見た目や重さはセメント瓦とほぼ同等です。
このように、モニエル瓦は一見するとセメント瓦と似ていますが、表面に独自のスラリー層を持つことが大きな違いです。したがって、メンテナンスには専用の手順や塗料が必須。これを知らずに通常のセメント瓦と同様の処理をすると、剥がれやすい、色落ちが目立つなどの問題が起こりやすいため注意が必要です。
モニエル瓦はどこに使われている?
モニエル瓦は、日本国内では主に 1980年代から1990年代にかけて 多くの住宅で採用されました。洋風住宅のデザインによくマッチし、色のバリエーションが豊富だったことから、特に南欧風や洋瓦風の仕上がりを好む施主に人気がありました。
当時は、新素材の屋根材 として高い防水性や美観性が評価され、セメント瓦の一種にもかかわらず、陶器瓦のような色の鮮やかさと高級感を演出できる点が注目されました。また、比較的安価で施工できるケースが多かったのも普及の理由の一つです。しかし、前述のとおりメーカーの生産終了により、今では新築住宅で使われることはほとんどありません。そのため、現在モニエル瓦が乗っている家は 築20〜40年程度 の住宅である可能性が高いと言えます。
- 洋風建築の一戸建て:スペイン瓦風や南欧風のデザインを採用した住宅に多く見られる。
- 開発分譲地の住宅:同じ時期に同じデザインの屋根材が一括採用されたケース。
- リフォームでカラフルなセメント瓦を導入した家:表面がスラリーで着色されているため、既存のセメント瓦とは異なる鮮やかな色合いを実現したい施主が選んだ例も。
もし築20年〜40年ぐらいの洋風住宅にお住まいの場合、屋根がモニエル瓦の可能性が高いです。既に生産されていないからこそ、補修や交換の際には一層慎重な判断が必要 だという点を理解しておきましょう。
モニエル瓦の見分け方!あなたの家の瓦はどれ?
モニエル瓦がセメント瓦や和瓦などと混同されやすい最大の理由は、見た目が非常に似ているからです。専門業者でも一見しただけでは分かりにくいことがあるほど。ただし、いくつかの チェックポイント や 他の瓦との違い を押さえておくと、素人でもある程度識別できるようになります。ここでは、そんなモニエル瓦の見分け方にフォーカスして解説します。勘違いして塗装や補修をすると後々大きな出費につながる可能性があるため、ぜひ正しい方法を学んでみてください。
簡単にできるチェックポイント
モニエル瓦を見分ける際には、表面の質感や裏面の刻印、そして年代 を確認することが重要です。特に、表面をよく見ると「スラリー層」と呼ばれる独特の着色層が確認できるかどうか が大きなヒントになります。
モニエル瓦は製造過程で、セメント製の基材の上にスラリー層をコーティングしています。時間が経つと、このスラリー層が剥がれたり部分的に欠けたりするケースもありますが、よく観察するとほかの瓦にはない独特の色の層が確認できます。また、製造メーカーによっては裏面にブランド名やロゴが刻印されている場合があります。かつて日本で生産されていたモニエル瓦には「Monier」や「スラリー」などの文字が刻印されていることがあるので、一枚をそっと外して裏面をチェック してみるのも有効です。
- 表面のザラつき:一般的なセメント瓦と比べると、モニエル瓦はややザラっとした質感を持つ場合が多いです。ただし、経年劣化が進んでいると差が分かりにくいこともあるため注意。
- 色の重なりや剥がれ:スラリー層が剥げると、下地のセメント部分が灰色っぽく露出することがあります。まだらに色落ちしている瓦は、モニエル瓦である可能性大。
- 裏面や側面の刻印:運が良ければ「Monier」「VIVA」「CTX」などの名称が刻印されているケースも。そうでなければ、セメント瓦用の一般刻印だけの場合もあり、判断材料には限界があります。
- 築年数:1980年代から1990年代に建てられた住宅の場合、モニエル瓦採用の可能性が高いです。
自分で簡易的に見分ける際は、表面の独特な塗膜(スラリー層) と 刻印、築年数 の3点をチェックしてみましょう。確信が持てない場合は、専門業者に相談 するのが無難です。間違った判断で施工に進むと、後から大きなトラブルになる恐れがあるので慎重に行動してください。
セメント瓦・和瓦との違いを写真で比較!
モニエル瓦とセメント瓦、和瓦の大きな違いは 表面の仕上げ と 形状、そして 重量感 にあります。写真や現物サンプルがあれば最も分かりやすいのですが、屋根の上に登らないと見えにくい部分もあるため、注意深く比較することが重要です。
- 和瓦:陶器製が多く、表面に釉薬が塗ってあるため独特の艶があります。また形状は緩やかなカーブを描く波型で、いわゆる「日本家屋」の風情を感じさせます。
- セメント瓦:モニエル瓦と同様にセメントが主材料ですが、モニエル瓦ほど分厚いスラリー層での塗装は行われていません。そのため、経年劣化の仕方や色落ちのパターンが異なります。
- モニエル瓦:セメント瓦に似ているものの、スラリー層が特徴的。洋風の形状も多く、鮮やかな着色とザラザラした表面が混在している印象があります。
-
和瓦 vs モニエル瓦
- 和瓦は光沢が強く、瓦同士がガチっと噛み合うようなデザイン。一方、モニエル瓦は「洋瓦」をイメージした形状が主流。塗料の剥がれが目立つと下地が見えやすい。
-
セメント瓦 vs モニエル瓦
- セメント瓦は単純にベース色で塗られていることが多いが、モニエル瓦は表面に一層の「スラリー」が重なっているため、剥離すると表面の色と下地の色がくっきり分かれやすい。
実際の写真を並べると、和瓦は釉薬による光沢や和風の形状、セメント瓦は塗装層が薄めでシンプル、そして モニエル瓦はスラリー層による独特の表面質感 と 洋風デザイン という違いがはっきりと見て取れます。もし屋根に上がる機会があれば、これらの点をチェックして間違いのない識別を行いましょう。
モニエル瓦のメンテナンスは要注意!間違った塗装はNG
モニエル瓦は表面の特殊なスラリー層により、他の瓦と同じ方法では上手く塗料が定着しない場合があります。よくある失敗として、「普通のセメント瓦用の塗料で塗装してしまう」「下地処理をせずにそのまま塗ってしまう」といったことが挙げられます。結果として、塗料がすぐに剥がれたり、美観を損ねたりする原因になるのです。ここでは、なぜモニエル瓦の塗装が難しいのか、そして 正しい塗装方法と手順、さらには DIYと業者選びのポイント までを解説します。
なぜモニエル瓦の塗装が難しいのか?
モニエル瓦の塗装が難しい理由は、主に スラリー層の存在 と 劣化の仕方 にあります。スラリー層は本来美観と防水性を高める役割を担っていますが、経年劣化で剥離しやすくなった状態に塗料を塗布しても、密着不良を起こす 可能性が高いのです。
通常のセメント瓦であれば、素地のセメントに対してプライマー(下塗り)や上塗り塗料を重ねるという工程で比較的安定した密着性が得られます。しかしモニエル瓦では、劣化したスラリー層が瓦の表面全体で均一に残っていない場合が多く、部分的に剥がれていたり薄くなっていたり します。その上に塗料をのせると、下地ごと剥がれる というリスクが高いのです。
- 一見キレイでも剥がれが進行:スラリー層が表面的には残っていても、内部からボロボロになっているケース。表面を高圧洗浄やケレン作業で丁寧に剥がしておかないと、新たに塗装しても数年で剥がれてくる。
- 密着テストの重要性:モニエル瓦用の塗料を使う前に、テスト的に一部分だけ塗装してみて乾燥後に剥がれないか確認する作業が欠かせない。
モニエル瓦の塗装は「スラリー層の状態」によって作業手順や使用する塗料が大きく変わります。適当な下処理や汎用塗料での施工は絶対に避ける ようにしてください。
正しい塗装方法と手順
正しい塗装手順は、「下地処理」→「専用プライマー」→「モニエル瓦対応塗料」での中塗り・上塗り の流れが基本です。最も重要なのは、下地処理でどれだけ劣化したスラリー層を除去し、瓦表面を均一な状態に整えるか にかかっています。
モニエル瓦の場合、表面のスラリー層がしっかり残っている部分と剥がれている部分の差が大きいと、塗料の付着にムラが発生しやすくなります。そこで、高圧洗浄やワイヤーブラシで 劣化したスラリー層を徹底的に削り落とす 作業が不可欠。次に、モニエル瓦用の専用プライマーを塗布することで、下地との密着性を高め、さらに専用塗料(弾性塗料や高耐候性塗料など)を中塗り・上塗りすることで防水性と美観を回復させます。
- 高圧洗浄 & ケレン作業:まずは水圧で汚れや脆弱なスラリー層を除去。固着した頑固な部分はブラシやヘラを使い、人力で削る。
- プライマー塗布:モニエル瓦対応と明記されたプライマーを使用。これを省略すると密着不良が起きやすい。
- 中塗り・上塗り:メーカーが推奨する乾燥時間を厳守。2回、場合によっては3回の上塗りを行うことで塗膜を均一化し、耐久性を高める。
大切なのは、下地処理の徹底 と 専用塗料の使用。この2点を守らないと、すぐに剥がれたり色落ちしたりといったトラブルが起きる可能性が非常に高い点を理解しておきましょう。
DIYは可能?専門業者に依頼すべきケース
結論から言えば、モニエル瓦の塗装をDIYで行うのは かなりリスクが高い です。屋根に上る危険性もさることながら、適切な下地処理や専用塗料の選定ができなければ 失敗する確率が高い でしょう。
モニエル瓦塗装の最大の難関は、前述した 劣化したスラリー層の除去 と 専用塗料の正しい扱い。DIYでやる場合、装備や経験が十分でないと、高圧洗浄機の当て方一つで瓦を破損してしまうリスクが高まります。また、屋根の勾配や足場の設置など、安全対策のコストもバカになりません。結果的に、DIYのはずが業者へ依頼した方が安く済んだ という事態も珍しくありません。
補修だけDIY:小さなクラックやコーキング部分の補修程度ならDIYで対応できる場合もあるが、屋根全面の塗装は専門業者のほうが無難。
- 足場代の問題:DIYでも安全を確保するためには足場を組む必要があり、資材のレンタル料などが高額になる場合がある。
- 専門的な塗装知識:下地処理のやり方や塗料の乾燥時間、気温・湿度管理など、正しく行うには専門的知識が欠かせない。
モニエル瓦は施工が難しく、DIYでのリスクが大きいため、基本的には専門業者に依頼するのがおすすめ。費用を抑えるなら、部分的な補修や点検を自力でやり、塗装など大掛かりな作業はプロに任せるという選択肢を検討してみましょう。
モニエル瓦の補修や交換の判断基準
塗装で対応できるケースもあれば、もはや交換しないと危険という状況もあります。モニエル瓦はすでに生産されていないため、交換が必要な場合の代替策 も頭に入れておく必要があります。ここでは、補修で済むケース と 交換を検討すべきケース の見極め方や、費用の目安について解説します。
補修できるケース vs 交換すべきケース
モニエル瓦の状態が 「部分的なひび割れや剥離」である場合 は補修で済む可能性が高いですが、屋根全体が著しく劣化している場合 や 雨漏りを起こすほどのダメージ がある場合は、交換(もしくは他の屋根材へのリフォーム)を検討すべきです。
生産終了しているモニエル瓦の場合、同じ瓦での差し替え が難しいケースが多々あります。部分的な破損であれば、業者が在庫として持っている瓦やリサイクル瓦で対処できることもありますが、広範囲に及ぶ場合は難易度が高くなります。また、築年数が30年以上経過している場合は、下地のルーフィング(防水シート)も傷んでいる可能性が高いため、葺き替えやカバー工法 を検討したほうが結果的にコストダウンにつながる場合もあるのです。
- 補修で済む事例:1〜2枚だけヒビが入っている、棟部分の漆喰が剥がれた、スラリー層の剥離が局所的など。
- 交換が必要な事例:屋根全体にクラックが多発している、大量の雨漏りが発生して天井裏の木部が腐食している、業者が在庫瓦を入手できないなど。
「屋根の一部だけが傷んでいるのか」「屋根全体が深刻な劣化を起こしているのか」をプロに点検してもらい、適切な判断 を下すことが大切です。無理に補修だけで乗り切ろうとしても、すぐに問題が再発する場合があります。
モニエル瓦の補修費用・交換費用の目安
モニエル瓦の補修費用は、部分補修の場合で1〜5万円程度、全面塗装を含む大掛かりな補修だと 50万円〜100万円前後 が一般的な目安です。交換や葺き替えを行う場合は、100万円〜200万円以上 かかるケースもあります。
屋根工事の費用は、使用する材料、作業範囲、足場の設置費用、施工地域の相場 など、様々な要因で変動します。モニエル瓦は生産が終了しているため、同じ瓦を入手する場合は 在庫や中古品に頼る 必要があり、瓦自体が高額になることも。また、交換の場合は「既存瓦の撤去費用」「新しい屋根材の材料費」「施工費」がすべて加わるため、高コストになりやすいのです。
- 部分補修のみ:1〜2枚程度の差し替えやスラリー層の剥がれ部分の補修→1〜5万円 程度。
- 屋根全面の塗り替え:下地処理やスラリー層の除去作業を含む→50〜100万円前後(2階建て30坪程度の住宅を想定)。
- 葺き替え・カバー工法:モニエル瓦を撤去し、新たに軽量金属屋根などを導入→100〜200万円以上(規模・地域・材料による)。
補修費用と交換費用には大きな差がありますが、長い目で見てどちらがコストパフォーマンスが良いか を考えることが重要です。築年数や劣化状態によっては、最初に高額でも交換したほうが結果的に安く済む場合もありますので、複数の業者から見積もりを取り、慎重に比較検討してください。
モニエル瓦のよくあるトラブルと対策
ここからは、モニエル瓦に特有のトラブル事例と、その対策方法を詳しく見ていきましょう。「塗装がすぐ剥がれてしまう」 という声や、「悪徳業者に騙された」 といった被害報告も少なくありません。正しい知識を持っておけば、不要な出費やストレスを回避できます。
塗装がすぐ剥がれる原因とは?
モニエル瓦の塗装がすぐに剥がれてしまう主な原因は、「下地処理の不十分」 と 「専用塗料の不使用」、あるいは 「気候条件を考慮しなかった施工」 などが挙げられます。
スラリー層がしっかりと除去・清掃されていないまま塗装すると、塗料が付着するのは「既に剥がれかけのスラリー層」になります。すると、そのスラリー層ごと剥がれてしまうのは当然の流れです。また、モニエル瓦専用の下塗り材・塗料を使わずに汎用品で済ませた場合も、密着性が十分確保できず短期間で剥離を起こします。さらに、気温が低い日や湿度が高い日に塗装を行うと、塗料の乾燥が不十分になり、剥がれやすくなるリスクが高まります。
- 施工後1年以内に剥がれ:下地処理を省略して安価に塗装を請け負う業者を選んだ結果、短期間で剥離が発生。
- 部分的に塗膜が浮いてくる:洗浄やブラッシングが甘く、脆弱なスラリー層が残ったまま塗装されたケース。
- 季節を選ばず施工:真夏の炎天下や梅雨時期に強行施工して、塗料の乾燥が不十分に。
モニエル瓦特有の塗装トラブルを避けるには、徹底した下地処理 と 専用塗料の使用、そして 適切な施工時期の選定 が不可欠です。短期間で剥がれないよう、施工品質を優先して業者を選びましょう。
業者選びのポイント!悪質業者に注意
悪質業者を選んでしまうと、高額料金を支払ったのにすぐ剥がれる、あるいは 本来必要のない工事を追加で提案される などの被害に遭う恐れがあります。業者選びでは、複数社からの相見積もり と 口コミや実績のチェック を徹底しましょう。
モニエル瓦は専門知識が必要なため、経験の浅い業者や悪質業者に依頼すると 「モニエル瓦向けの施工ができないのに、セメント瓦の要領で工事してしまう」 というトラブルが発生しやすいのです。また、「今すぐ工事しないと雨漏りがひどくなる」などと不安を煽り、高額な工事を強要するケースも見受けられます。信頼できる業者は 施工事例を具体的に見せてくれ、適切な下地処理と材料を説明してくれるはずです。
- やたらと値引きを強調する:相場の半額以下など、不自然に安い見積もりを出してくる業者は要注意。
- 保証内容が曖昧:施工後すぐ剥がれても「自然劣化」「施工外の原因」と言い逃れるような曖昧な保証は信用できない。
- 過度な不安を煽る:「今すぐやらないと取り返しのつかないことになる」というセールストークは危険信号。
大切なのは、複数の業者を比較検討する こと。料金や施工方法、使用材料、実績をしっかり確認し、安心して任せられるところに依頼しましょう。モニエル瓦の施工経験が豊富な業者であれば、成功事例や具体的な作業工程をきちんと説明してくれます。
まとめ|モニエル瓦の正しい見分け方&メンテナンスで後悔しない!
ここまで、モニエル瓦の基本的な特徴や見分け方、そして塗装・補修・交換のポイントや注意点を 徹底的 に解説してきました。改めて重要な点を整理し、「失敗しないために何をすべきか」 を明確にしましょう。
モニエル瓦は一見するとセメント瓦に似ていますが、スラリー層という独特のコーティング を持ち、経年劣化の仕方や再塗装の難易度が高いという特徴があります。正しい見分け方 と 専用のメンテナンス方法 を知っていれば、瓦の寿命を延ばし、余計な出費を避けることができます。
- 製造終了:既に国内生産は終了しており、交換部材の入手が困難。
- スラリー層の劣化:塗装が剥がれやすい、色落ちが目立つというトラブルが多発。
- 誤施工のリスク:普通のセメント瓦と同じ要領で塗装すると、すぐ剥がれる可能性大。
- 見分け方:築年数、裏面の刻印、表面のスラリー層の有無をチェック。
- メンテナンス手順:高圧洗浄で徹底的に劣化部分を落とし、専用プライマー・塗料を使用。
- 補修 vs 交換:部分的なヒビなら補修でOK、屋根全体が劣化しているなら葺き替えやカバー工法も検討。
- 悪質業者に注意:相場より極端に安い見積もり、曖昧な保証、過度な不安を煽るセールストークは疑う。
モニエル瓦の維持管理で失敗しないためには、「正しい見分け方」「適切な下地処理」「専用塗料の使用」「信頼できる業者選び」 の4つが鍵となります。もし、この記事を読んで少しでも疑問や不安がある方は、決して独断でDIYに走るのではなく、プロに相談 してみることをおすすめします。
以上が、モニエル瓦の正しい見分け方から塗装・補修・交換までを徹底解説したブログ記事の完成版です。スラリー層を持つモニエル瓦の特性 をしっかり理解し、長持ちする施工 と 無駄のないメンテナンス を実現していただければ幸いです。万一、ご自身での判断が難しい場合は、ぜひ一度プロに相談してみてください。あなたの屋根が、これからも安心して過ごせる空間を守るために役立ちますように!
株式会社イワショウは岡山市北区、南区、中区、東区、赤磐市、瀬戸内市、備前市などを中心に



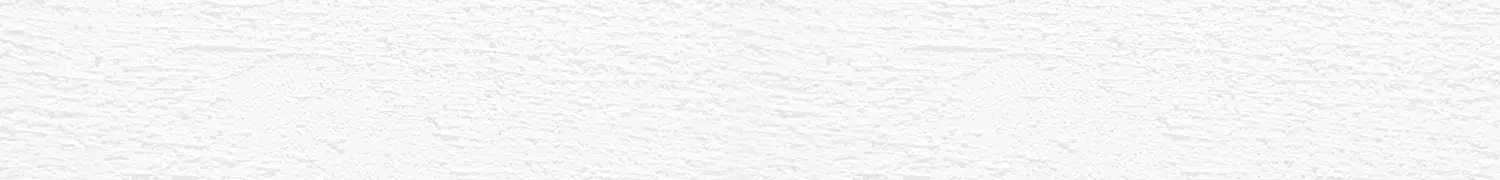
.webp)